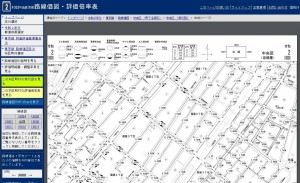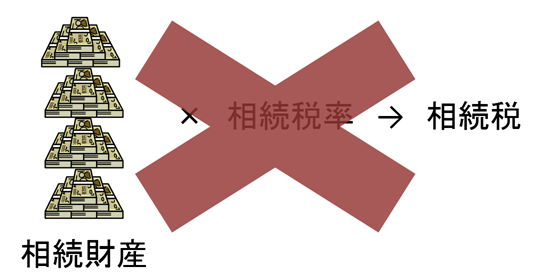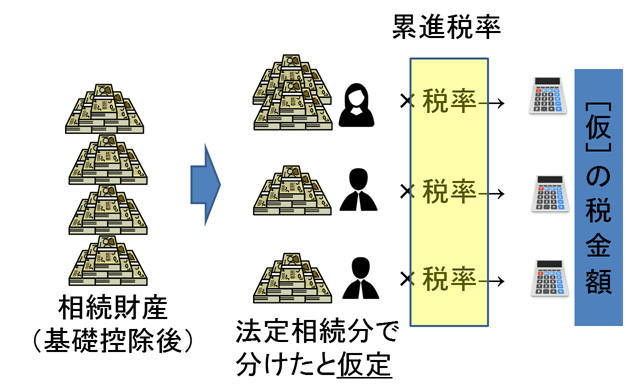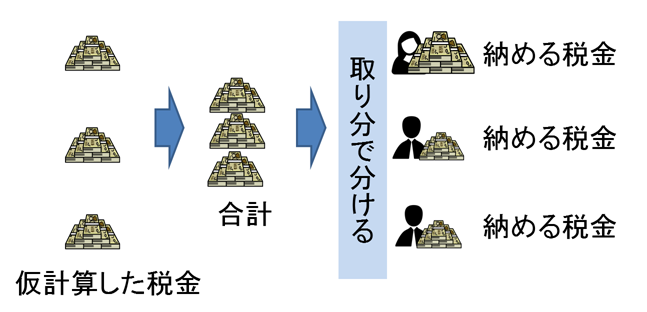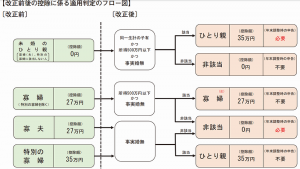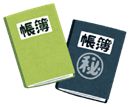私たちの事務所名にもなった「耕夢(こうむ)」。
日本どころか世界のどこにもないコンセプトで作られた、会計事務所の業務管理用アプリケーションです。
このシステムを機能面で紹介することはもちろん可能なのですが(セールスフォースさんのページにもご紹介あり)、実際どのように使われているかを比較ストーリー形式で書いてみました。
この内容、特に誇張はなく、実際にそれぞれの事務所で起こっていることがほぼそのまま書いてあります。
では、会計事務所の一日を少しだけご覧ください!
====================================================
<7:30am>
(耕夢)
所長が出所。通勤中の電車で「内部chatter」に研修担当職員が掲載した会計・税務等の最新業界誌を読み、知識をアップデートするとともに必要な論点を「耕夢チェックリスト」に反映していく。また、お客様に関連する情報があれば、お客様それぞれに用意された「外部chatter」で早めに情報を提供しておく。
また、昨晩から今朝にかけて事務所に届いたFAXも紙で出力されず「内部chatter」に掲載されているので、全て確認の上対応が必要な場合は、そのFAX自体にコメントをつけ、各担当職員への指示を出しておく。
ここまで全てスマホやタブレットだけでOK。
(旧来事務所)
所長は早めに出所するよう心掛けているが、各担当の業務進捗は朝礼まで不明。机の横に溜まった業界誌を「読まなきゃな」と思いつつ、昨晩返事できなかったメールの返信と、昨日事務所に居なかった際に積まれた書類・郵便の山で時間を取られる。もちろん紙で出力されたFAXは担当が出所するまで放置。
<08:45am>
(耕夢)
職員が出所。掃除やシステムメンテナンス、郵便の受け取り、有給管理、小口現金、消耗品管理・発注など総務的業務も「総務チェックリスト」の「期日到来・未実施チェックリスト」を参考にしながら漏れなく総務業務を行っていく。
業務時間が始まると、まずは「直近スケジュール」で自分に加えて所長、他の職員の2週間分のスケジュールを確認。他の職員のスケジュールに給与計算やお客様との面談など「クリティカル業務」マークの付いたものがある場合、体調不良による休みはもちろん、お子さんの急な発熱により保育園に預けることができなかった場合の「在宅切り替え」など、バックアップ対応を皆で検討しておき、カバーしきれない場合は所長に報告して対処を頼んでおく。
(旧来事務所)
職員が出所。朝礼までに掃除などを進めるが、特にマニュアルはないのでベテラン職員の経験次第で、時々抜けることがある。
9時からは30分ほどかけて朝礼。本日行う業務や来所予定、申告期限などの確認を行うものの、報告方法や内容もメモや口頭で、網羅性の確保やフォローアップは難しい。本日急に体調不良で休んだ職員の担当業務については、業務進捗は本人しかわからず、とりあえず「何かあったら所長に相談する」ことにした。
<10:00am>
(耕夢)
朝一の業務が終了したので、次は今月が決算期末のお客様の決算書・申告書作成。耕夢(こうむ。案件のこと)ごとに用意されたチェックリストを見ながら、漏れのないよう作業を進めていく。チェックリストのスケジュールに基づき早めに資料を依頼しているため滅多にないが、追加資料が必要となった場合も「外部chatter」で依頼、お客様からはファイルを添付してすぐにお送り頂く。「外部chatter」のセキュリティは十分に確保されているので、ファイルもパスワードなしで添付して頂いてOK。
(旧来事務所)
それぞれが自分のカレンダーにメモ書きした業務をスタート。決算作業は前年の踏襲と各担当の経験に基づいて進める。しばらくして資料が足りないことに気づき、電話でお客様に依頼したものの、届くのは明日。他の業務も取り立ててないので(実際には見えていないだけ)手待ちになる。
<12:00pm>
(耕夢)
全員不在を避けるためランチタイムはシフト制としているが、担当が不在の際お客様から問い合わせがあっても、「外部chatter」でのやり取りやその他お客様関連データ、経緯は全て掲載されているため、担当以外でも即座に対応が可能。
(旧来事務所)
お昼に出ようと思ったら、お客様から問い合わせのお電話が。運の悪いことに本日お休みの職員が担当しており、状況も資料もわからない。仕方がないのでその職員の携帯へ電話するが、病院へ行っているのか連絡がつかない。お客様には「申し訳ありませんが職員が不在で」とお詫びの電話を入れる。所長はランチを兼ねて夕方まで外出してしまい、これまた電話に出ない。
<1:00pm>
(耕夢)
所長が新規ご紹介先の工場を訪問のため外出。スキャンされた名刺がデータ化され、あらかじめ顧問先データ登録が完了しているので、スマホアプリから登録された電話番号に電話することも可能。また、登録された住所は地図に変換されてスマホのナビにそのまま転送されるため、徒歩、車、公共交通機関などを使った詳細なルートと所要時間が即座に表示され、初めての訪問でも迷いや遅れがない。
(旧来事務所)
所長はフットワークが軽いのはいいが走ってから考えるタイプのため、外出してから「あのお客様の連絡先どうだったっけ」「○○の資料送って」「迷ったからちょっと遅れると連絡入れといて」など、職員頼みの行き当たりばったりな行動が多くなってしまう。そのたびに職員の作業は止まり、生産性は下がっていく。
<2:00pm>
(耕夢)
午前中に行われた業務で耕夢の進捗割合が変わったので、それをトリガーとして自動で「内部chatter」に進捗度が掲載される。また、月次試算表が完成したら、これもPDFで「外部chatter」に掲載、社長向け伝達項目となる今月のトピックなどもコメントしておく。耕夢のリストには進捗度に応じて作物の育成段階を模した動くアイコンが設定されており、「(辛い)仕事」ではなく「お客様のために丹精込めて作物を育てる」イメージが持てて面白い。
また、隙間時間も前倒しの仕事はもちろん、「期日経過・未完了ダッシュボード」を確認し、少し遅れ気味な他の職員の耕夢に関するチェックリストを代わりに実施したり、chatter掲載の業界誌を読んだりと、手待ちになることはほとんどない。
(旧来事務所)
資料の遅れもあり、集中月の決算作業は遅れがち。前年度も申告期限ぎりぎりになって税額や報告予定日のご連絡をしたので今年はなんとか早くしたいが、昨年辞めた職員の後を引き継いだためまだ業務に慣れず、マニュアルもなく過年度の資料を見ながら進めるのでなかなかスピードが上がらない。自分はバタバタしているのに、手待ちで所長が居ないのをいいことにネットを見ている職員がいるとストレスがたまり、はや転職を検討している。
<3:00pm>
(耕夢)
他の担当が仕上げた決算の「検算」を、副担当として実施。該当するお客様の「チェックリスト」を表示し、一つ一つの項目がきちんと実行されているかを確認していく。ドラフト決算書や申告書も「chatter」にて掲載が可能となっているので、出張先や在宅でも、またタブレットでも検算作業が可能となっている。
検算により発見された特定の事項は「チェックリスト」の「添付書類コメント」に記載する。このコメントにはタグが付けられており、「税理士法33条の2の添付書面(税務調査のリスクを減らす書類)」への記載事項へ自動的に転記される。またこれらのタグは、チェックリストそのものの改訂、消去を指示する場合にも利用できるようになっている。
(旧来事務所)
決算は完成したが、所長が不在で、他に内容を知る者もいないので、とりあえず印刷して注意事項やまだもらっていない書類などを付箋に書いて所長の机の上に置いておく。以前別のお客様で税務調査があった時、チェック漏れで大きな失敗を指摘され、お客様からも所長からも叱責された記憶がちらつく。もっと勉強しなきゃとも思うが、なかなかその時間も取れなくて不安が募る。
<4:00pm>
(耕夢)
保育園のお迎えがある短時間職員が退所。明日は乳幼児健診があるため在宅勤務の予定だが、留意事項は関連する「chatter」に記録してあるため、業務はシームレスに進めていける。
また、どうしても質問の必要な場合「内部chatter」で資料を添付して問い合わせをしておけば、スマホアプリでお迎え後など手の空いた時間に簡単な回答を貰うことも可能となっている。
(旧来事務所)
病欠の職員とようやく連絡がつき、午前中の質問事項をお客様に伝えることができた。このやり取りで取られた時間はかなりのものだが、表向きは自分の仕事が進まなかった結果しか残らず、なんだか損した気分になる。今結婚を考えている相手がいるが、出産、育児をこの環境で乗り越えられるとは思えず、非常に悩ましい。
<5:00pm>
(耕夢)
業務をこなしながら、お客様とは「外部chatter」を中心に密なコミュニケーションを取っておく。電話やメールでも連絡は可能であるが、「税理士法41条に規定する業務処理簿」に記載すべき税務に関する質問・回答や、どんな業務を行ったかといった情報は、chatterを使えば二度手間がなく効率的で、正確かつ分かりやすい。パソコンメールすら使えないお客様でもSNS的な使い勝手のスマホ向けchatterアプリは馴染みがあるし、資料のコピーもその場で撮影したものを鮮明に投稿できるので、業務に関連しそうな書類はすぐ掲載される。使い勝手の良さから「パソコンよりこっちの方が便利」という年配の経営者も出てくるほど。
(旧来事務所)
定時終了間際に、お客様から電話とFAXで「明日が期限なので今日中にこの資料を作って欲しい」と頼まれる。内容を見ると2カ月前にはわかっていたことで、その時一言入れておいてくれれば…という言葉をぐっと飲みこんで残業を覚悟する。何時も「ほうれんそうが大事」と言っている所長にはメールで報告しておくが、返事がなく読んだかどうかすらわからない。
<5:30pm>
(耕夢)
業務時間終了少し前に、「スケジュール」と「実績」を入力。スケジュールは、今後最低でも2週間程度の業務予定を日時(開始・終了)を指定して記載し、また、実績については先に書いてあるスケジュールを基礎とし、それぞれの耕夢単位で実際にかけた時間を入力する事で効率的に記録できる。総務業務や担当外のヘルプ業務を行った場合でも実績として記録され、業務実績の評価は正当に行われる。
実績が記録されると「内部chatter」に「退勤記録」が自動的に掲載され、定時できちんと退所できたことが出張中の所長にも確認できる。また、上手にヘルプ業務を行った場合や難しい課題を解決した場合には、所長や職員から「いいね」やお礼のコメントがついてくる場合もある。
有給休暇も内部売上を割り当てられた「耕夢」の一つとして扱われており、予定を登録することで自動的に「内部chatter」に申請が行われる。承認はその申請に所長が「いいね」することで完了する。有給休暇の累積と残り日数はレポートで自ら確認できるので、業務の状況にも配慮しつつ無理のない消化が可能となっている。
(旧来事務所)
急ぎの書類作成は意外と計算が難しく、終わる気配もないまま定時にタイムカードを押せない日が続く。本日積み残しの仕事はとりあえず明日以降に回すしかなく、「こんなに忙しいのに何考えてるんだ」と言われて有給すら取りづらい。
<7:00pm>
(耕夢)
所長が出張先から自宅へ直帰。その間にスマホアプリで本日実施された業務やその時間、耕夢の割り当て状況、お客様ごとの採算に目を通しておく。お客様とのやり取りや事務所内外での通知事項だけではなく、耕夢の進捗状況やチェックリスト改定内容、受信FAX、送付状控など全てが内部・外部chatterに記載されているので、これらをブラウズしておけば翌日に持ち越すことなく連絡や意思決定を行うことができる。
(旧来事務所)
ようやく書類ができたので、お客様にFAXして業務終了。置きっぱなしの決算書の上へさらに控を置いて、帰り支度を始める。明日この件で朝礼後時間がとられると、溜まった仕事がまた遅れてしまうとうんざりする。