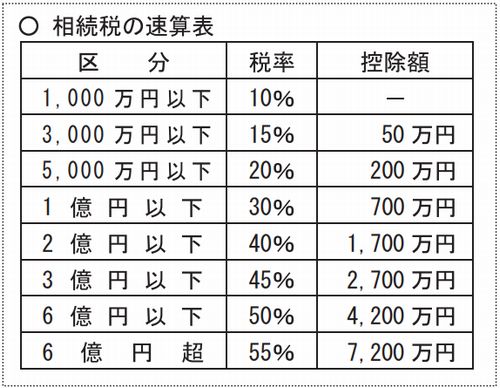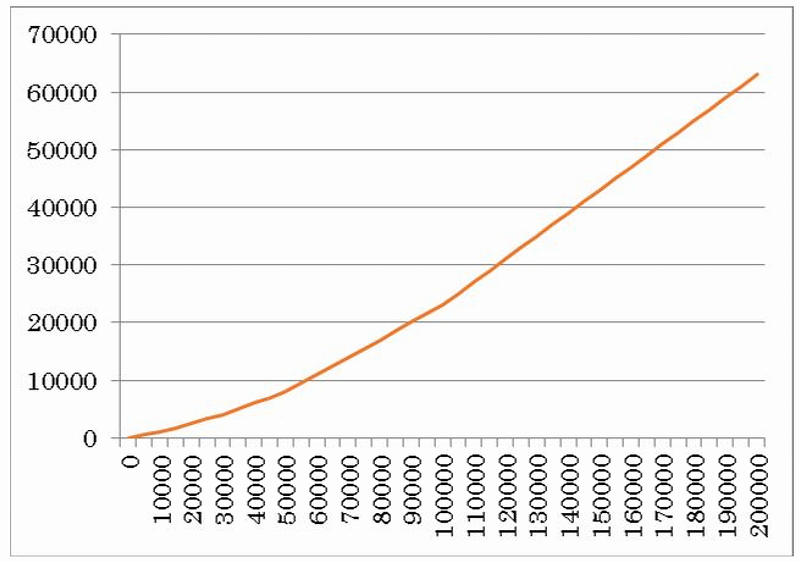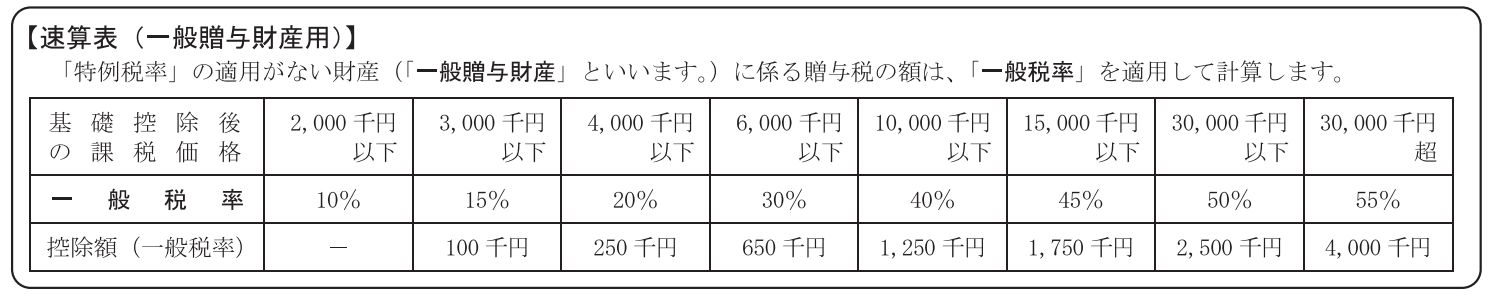私たちの事務所は、「税理士法第33条の2に規定する添付書面」をさまざまな税務申告書とともに税務署へ提出しています。この書面、経営者が懸念する「税務調査」のリスクを大きく減らす効果があります。最近※も2件「税務調査省略」事例が出ましたので、うち1件をご紹介します。
なお守秘義務がありますので、正確な時期や業種、登場人物は少しぼかしてあります。
※当該記事は2019年公開のメルマガから転載されています。
1.税務調査のリスク
法人税や所得税、消費税、相続税といった「申告納税方式」の税金は、「納税者が自主的に申告、納税する」事を建前としています。
ほとんどの方はこの申告と納税を適切になさっているのですが、ごく一部の悪意を持った脱税や、ルールや法律の理解を誤った場合など、税金の計算が過少になるケースも無視できません。このため、申告納税方式の税金には必ず「税務調査」がセットになっています。
この税務調査、誤りが見つかったら「追徴課税」といって追加で納税させられたり、加算税や延滞税といったペナルティがつく場合もあります。悪質な場合には重加算税といった重いペナルティに加え、刑事罰を課される場合もあります。
弊害はそれだけではありません。上場準備中の会社の場合税務調査を受けるリスクは高くなる(こちらの記事を参照)のですが、そこで重加算税などの重いペナルティを受けると、上場準備そのものが頓挫してしまう可能性もあるのです。
税理士法第33条の2の添付書面は、税理士が決算・申告に関する一定の事項を記載した書面を申告書とともに税務署へ提出する事で、これらの税務調査のリスクを大きく下げる(またはゼロにする)ことができる、画期的な制度です。
但し、この書面を提出するには、捺印する担当税理士が申告書提出までの業務について深く知らねばならず、また多くの文章を書く必要もあって手数が掛かります。このためもあってか、現在も申告書に対する書面添付割合は1割にも満たないと言われています。
2.税務署からの打診
税理士に依頼(委任)している方の場合、税務調査の対象になったら(税務調査の対象に選ばれるのはどのような場合かについてはこちらを参照)担当の税務署員から「原則として担当税理士に」税務調査日程の調整について電話が掛かってきます。直接電話したり、急にやってきたりすることはありません。これだけで税理士に依頼するメリットが十分あるというものです。
「税理士法添付書面」を提出している場合、税理士に電話が掛かってくるのは同じなのですが、税務調査の日程調整には入らず、税理士と税務署員との打ち合わせ(「意見聴取」)日程の調整となります。
今回も、4月初めに確定申告が終了して一時的に忙しさが落ち着く時期に連絡がありました。
3.事前の資料準備
意見聴取日程が決まりましたので、当日の資料を準備します。
決算や申告に関する詳細な内容は「税理士添付書面」に記載してありますのでほとんど説明は不要かと思われるのですが、そこは単なる文書、先方がこちらの意図した通り理解しているとは限りません。ということで、領収書・請求書といった補足資料や条文解釈の資料、場合によっては総勘定元帳などのデータを揃えておきます。
4.意見聴取当日
事前の打診時に決めた日時、準備した資料とともに税務署へ向かいます。当然ながらこの時点で納税者の方は同行はもちろん、他に何もする必要はありません。
税務署の担当部署に到着すると、調査官が出迎えてくれます。税務署は怖い所と思われているかもしれませんが、皆さんとても丁寧で穏やかです。
ご挨拶や雑談のあとは本題に入ります。納税者に関して、税理士法添付書面や持参した書類をもとに、税理士が詳しく調査官に対して説明し、これに対して調査官からも追加の質問などがあります。
これら一連のやり取りは、実は税務調査で行われるものの「縮小版」ともいえる手続なのです。従って、簡単なように見えてこの意見聴取を確実に進めるには税務調査立ち合いに十分な経験がある税理士が対応しなければなりません。
さて今回のケースは、少し残った疑問について2点ほど追加資料の提出を依頼されて終了となりました。
5.調査省略
事務所に戻り、早速追加資料を作成します。
今回依頼された資料は、特定の取引先に関する売上や外注費、その入金・支払に関するものでしたから、比較的簡単でした。
お客様に承認頂き、これらの資料を郵送したら完了です。
その後特に問題がない場合は、1~2週間待っていると、税務署から「調査は省略することになりました」というお電話を頂くことができます。
ただこの電話はあくまで内定で、完全に調査が省略される場合には「意見聴取結果についてのお知らせ(国税庁HPの文書例)」という書面が届き、正式に調査省略となります。
6.書面添付、意見聴取について
この制度、きちんと実践するには手間がかかりますが、申告書の品質は確実に上がります。そのため、第一義的には納税者や税理士が助かる制度であるものの、国税側も非常に力を入れていて調査官の協力体制も十分です。税務署はよく「税金を取ることだけを考えている」と思われていますが、一番大事なのは「法律通りの適正な申告・納税を行ってもらう」ことなので、こういった「真っ当な納税者の負担が減る」制度はあちらにとっても大きな意義があるのです。
しかし、それにもかかわらず税理士側の都合でなかなか使われていないのは正直残念なところです。
もし新たな税理士さんと契約される場合、「税理士法添付書面をつけてもらえますか?」と聞いてみては如何でしょうか。多くの税理士はいろいろな理由を述べて「意味がない」などと断るのですが、もし自信をもって「100%添付しています!」という税理士さん(若い方に多いです)でしたら、小さな規模でも是非契約を検討して見て下さい。