のっけから「倒産」に触れます。
私は以前、いわゆる「倒産系」と呼ばれる、破産や清算、民事再生といった業務に数多く関与させて頂きました。
また、90年代から現在に至るまで、中小企業を中心に税務や会計の業務にも携わってきました。
そこで実際に体験したのは「中小企業は赤字で倒産する訳ではない」という絶対の真理です。
毎年毎年赤字を出し続ける会社が生き残り、売上がどんどん伸びて利益の出ている会社があっという間に倒産する、ということも全く稀なケースではありません。
結局、中小企業の倒産原因は、そのほとんどが「資金繰りに失敗する(ショートする)」ためであると言っても良いと思います。
中小企業における資金繰り管理はそれほど重要であり、単なる現預金の増減把握に留まらず、事業の継続可能性そのものに直結する重要な業務なのです。
では、その大切な資金繰りを間違わないためにはどうすればよいでしょうか。
まず注意すべきは、「資金繰り計画の可視化」です。
損益計算書上の黒字と、実際の資金繰り状況は必ずしも一致しません。
商売をしてみれば分かりますが、「売上は上がった瞬間に資金になる」「支払は仕入れや費用が発生した瞬間に行われる」ものではなく、通常はそれぞれの入金や支払が数日~数か月ズレて行われるからです。
例えば、大きな利益の出る売上を上げて大喜びしたとしましょう。
しかし、その売上のための仕入れや経費、給料の支払いが今月末で、売上の入金は来月末、となればどうでしょうか。
売上が大きければ大きいほど、「先に支払うべき費用も大きい」すなわちその時点で資金がショートしてしまう可能性も大きくなるのです。
このような事態を防ぐには、月次の資金繰り表(将来の入出金予定を一覧化した表)を作成し、資金の流れを体系的に整理し、あらかじめ資金がどれくらい必要になるかを把握、対応することが不可欠です。
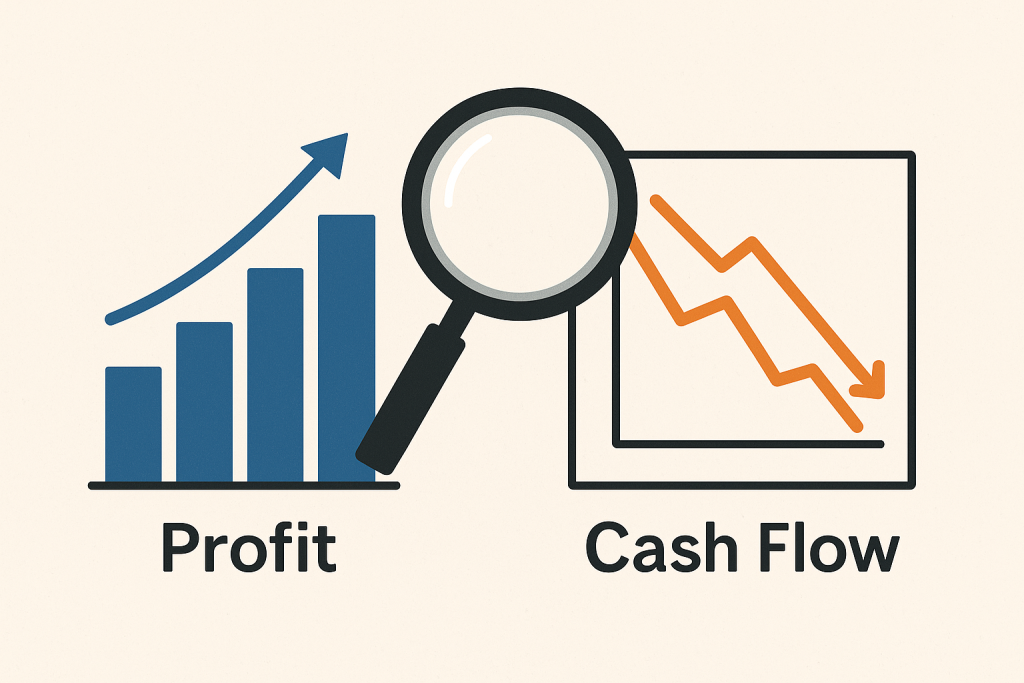
特に、売掛金の回収サイト(売上代金が実際に回収できるまでの期間)と、買掛金の支払サイト(仕入代金を支払うまでの期間)の差によって生じるキャッシュフローのギャップ(資金の出入りのズレ)を正確に把握することが、資金ショートを防ぐ鍵となります。
次に、金融機関との関係構築についてです。
資金調達は、必要に迫られてからではなく、平時から備えておくべきものです。
具体的には、事前に財務内容を金融機関に説明し、信用を高めておくことが重要です。
借入枠(あらかじめ設定しておく融資限度額)を確保したり、コミットメントライン契約(一定期間、必要に応じて融資を受けられる契約)を締結するなど、将来の資金需要に備えた対策を講じておくべきです。
また、銀行担当者とは定期的に情報交換を行い、自社の状況を正しく理解してもらうことが、いざというときの迅速な資金調達につながります。

売上債権や棚卸資産の管理も欠かせません。
売掛債権の回収遅延は、資金繰り悪化の大きな要因ですので、取引先の信用リスク(債権回収不能リスク)の管理や、与信限度(取引上限額)の設定、請求漏れ防止の仕組みづくりが求められます。
また、棚卸資産(在庫)についても、過剰在庫は資金を圧迫するため、適正在庫水準の維持や在庫回転率(一定期間に何回在庫が回転したかを示す指標)の改善に努める必要があります。
さらに、資金繰り悪化の兆候を早期に察知する体制づくりも重要です。
例えば、月次決算を適時に実施し、売掛金回収期間の延伸、仕入債務返済の遅延、運転資金需要の急増などの指標をモニタリングすることで、問題の兆しをいち早く捉えることができます。
このモニタリングを精緻かつ適時に行う事は大変難しいのですが、最近は様々なツールやサービスが提供されており、専門家や経理のベテランでなくてもコントロールすることができるようになりつつあります。
弊所もお客様向けにツールを開発・運用しており、導入頂いたお客様から一定の評価を頂いています。
倒産しないために~資金繰(しきんぐり)の重要性と便利なツール
資金繰り対策は、一時的な融資や返済条件変更だけでは解決できません。
日常の資金管理体制を地道に整備し、中長期的な財務戦略を描くことが、持続的な企業経営を支える土台となります。
私たちも全力でお手伝い致します。